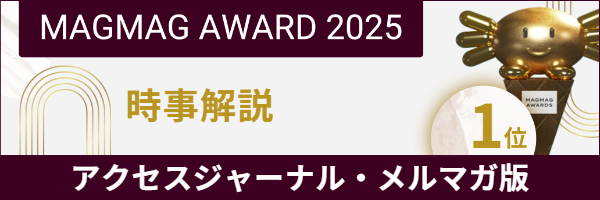筆者・田沢竜次(フリーライター)。1953年東京生まれ。編集プロダクション勤務などを経て1983年からフリー。85年『月刊angle』連載を基に『東京グルメ通信・B級グルメの逆襲』(主婦と生活社)を書き下ろし、また文春文庫の「B級グルメ」シリーズでも活躍。B級グルメライターとして取材・執筆を続け今日にいたる。一方、大学の映画サークルで自主上映するほど映画にも精通。著書に「B級グルメ大当りガイド」「ニッポン映画戦後50年」など。
 前々回の「さらば丸の内東映」の回で、少しだけ触れた地下の「丸の内東映パラス」。ここで観た『悪魔のいけにえ』(トビー・フーパ―監督)が、ずっと後になってホラー映画の金字塔とも呼ばれ語り草になり、最近でも4K版で特別公開されたりして、50年経っても色褪せていない。しかし公開当時は、たまたまテレビで(どんな番組だか忘れたが)「すごい映画が公開される」と予告編を観ていた。
前々回の「さらば丸の内東映」の回で、少しだけ触れた地下の「丸の内東映パラス」。ここで観た『悪魔のいけにえ』(トビー・フーパ―監督)が、ずっと後になってホラー映画の金字塔とも呼ばれ語り草になり、最近でも4K版で特別公開されたりして、50年経っても色褪せていない。しかし公開当時は、たまたまテレビで(どんな番組だか忘れたが)「すごい映画が公開される」と予告編を観ていた。
確かに今まで観たこともない不気味でショッキングなシーン(特に人間の皮でつくった面をかぶった大男がチェーンソーを振り回して追っかけてくる)に仰天して、封切りの初日に丸の内東映パラスに駆けつけたのだ。まだスプラッターとかスラッシャーといった言葉もなく、後々の『13日の金曜日』とか『ハロウィン』といったモンスター化するシリーズものや、サイコキラーものとは違って、新鮮でジャンクな恐怖感に打ちのめされたね。 低予算の制約とかで役者も無名、節約のために16ミリフィルムで撮影した粒子の荒い画面がリアリティを醸しだしていて、ヒッピー風の5人組が次々に餌食になる展開やシュールな結末も(警察も出てこないし)、アメリカン・ニューシネマ風でもある。何といってもレザーフェイスのチェーンソー男の謎めいたキャラクター(最後まで素顔も見せないし口もきかない)が最高で、後々になって伝説化するのだが、封切り当時は、ゲテもの扱いで、映画評論家からも無視されていたってわけだ。
低予算の制約とかで役者も無名、節約のために16ミリフィルムで撮影した粒子の荒い画面がリアリティを醸しだしていて、ヒッピー風の5人組が次々に餌食になる展開やシュールな結末も(警察も出てこないし)、アメリカン・ニューシネマ風でもある。何といってもレザーフェイスのチェーンソー男の謎めいたキャラクター(最後まで素顔も見せないし口もきかない)が最高で、後々になって伝説化するのだが、封切り当時は、ゲテもの扱いで、映画評論家からも無視されていたってわけだ。