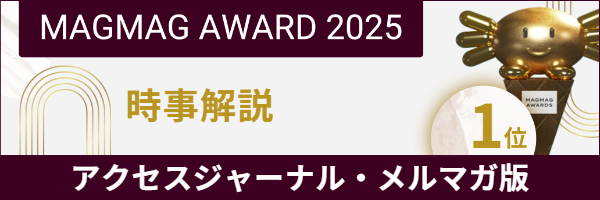プロフィール 投資歴26年、兼業投資家。投資で勝つために必要なのは、1に「メンタル」、2に「需給」を読む力、3に「ファンダメンタルズ分析」だと考えている。安定した資産形成を促すことを心がけている。
プロフィール 投資歴26年、兼業投資家。投資で勝つために必要なのは、1に「メンタル」、2に「需給」を読む力、3に「ファンダメンタルズ分析」だと考えている。安定した資産形成を促すことを心がけている。
≪先週の相場振り返りと今週の見通し≫
先週金曜日の日経平均株価の終値は、37,742円と前稿比-223円(※前項比+805→ +594→ +251→ +672→ +1125→ +976→ +1144→ ▲195→ ▲3339→ ▲557→ +624 →+166 →▲269→▲1621→ ▲372→ +362→ ▲785→▲360→+1481→▲739→▲705→+193円(大納会))となった。
週末金曜日の夜、米国の5月雇用統計が堅調な数値で発表されると、ドカーン!と火柱を上げるように日経平均先物は38,000円台まで上昇したものの、米国市場が始まると上げ幅を縮め日経平均先物6月限は37,985円で引けている。
2025年の最安値は4月7日(月)30,793円。2024年8月5日は31,156円のフラッシュクラッシュがあった。
 ドル建て日経平均の終値は262.1ドル(※263.8→259→260→257.9→253.8→248.5→244→233.3→231.3→246.3→252→249.3→250→247.7→257.7→256.5→255.8→255.8→257.3→247→247.5→252.6→246.7(大納会))。こちらは今年の最高値は264.9ドルを最高値。最安値は4月7日に211.2ドルがあった。
ドル建て日経平均の終値は262.1ドル(※263.8→259→260→257.9→253.8→248.5→244→233.3→231.3→246.3→252→249.3→250→247.7→257.7→256.5→255.8→255.8→257.3→247→247.5→252.6→246.7(大納会))。こちらは今年の最高値は264.9ドルを最高値。最安値は4月7日に211.2ドルがあった。
NYダウは、週間で+493ドル高となる42,763ドル(※前稿比+667→▲1052→+1406→▲68→+1203→+972→▲1071→+1898→▲3269→▲401→+497→▲1314→▲1039→+413→▲1,118→+243→▲242→+121→+936→+1550→▲794→+151→▲259)。※最高値は2024年12月5日の45,074ドル。※4月7日に36,612ドルが直近最安値。
ナスダック100指数は21,762Pと、前稿比+421P高(※前稿比+425→▲512→▲1367→▲42→+670→+1175→▲702→+1562→▲1,883→▲473→+49→▲496→▲683→▲730→▲501→+624→▲23→▲296→+333→+594→▲450→+183→▲175)であった。※4月7日に16,542ドルが直近最安値。
先週金曜日の夜は、PM21:30「米国雇用統計」の発表後、日経平均先物は一気に100円幅で上昇する、まるで噴火したような上げ方をしたためド肝を抜かれたが、NY時間が始まってしまうと30分もたずに(PM11:00前)にしょんぼりした値動きとなって、そのまま大引けを迎えている。これをみた筆者は2つ思うことがあった。
1つ目。今回の雇用統計の中身をみるに、100円幅でドカーンと上がるほど発表された内容にサプライズはなかった。ということはまだ相当数、買い遅れている筋がいるということである。
そして2つ目。トランプの仕掛ける関税政策の影響が不透明すぎて、日経平均株価指数は、38,000円を上抜けられるような外部環境ではない、ということだ。関税政策自体は、だいたい米国に対して10%~15%程度で織り込んでいるとはよく聞かれるが、話はそういうことではなく、そうなった後、米国経済含めて世界経済がどうなるか? これがたいへん不透明だということである。
 そもそも現状の米国の関税交渉は、英国とだけ合意できたものの、その後どこの国とも合意ができていない。日本に関しても週末土曜日に、「一致点が見いだせない」という赤沢大臣発言が記事化されており、もう5回目の交渉であることからして、そろそろ米国から突き放される可能性があるだろう。そもそも、交渉がうまくいっていたはずのインドに至っても、直近はなんの音沙汰もなくなったように思う。
そもそも現状の米国の関税交渉は、英国とだけ合意できたものの、その後どこの国とも合意ができていない。日本に関しても週末土曜日に、「一致点が見いだせない」という赤沢大臣発言が記事化されており、もう5回目の交渉であることからして、そろそろ米国から突き放される可能性があるだろう。そもそも、交渉がうまくいっていたはずのインドに至っても、直近はなんの音沙汰もなくなったように思う。
今週も週初に米中交渉が行われるが、まぁこの両国に進展があるわけないだろうし、そもそも各国、いまは様子見モードになっているようで、G7サミットが行われる来週まではどこの国とも関税交渉の合意の材料がでないのではないかと感じている。
さて、今週のストラテジーに移りたい。
筆者はS&P500株価指数が6,000Pに到達した今、「ここからどう動いていくか?」に大きな注目をしている。というのも今週の日本は週末にメジャーSQを迎えるので、週初(水曜日あたりまで?)は、特に相場変動が大きくなりやすいだろうが、いまのところ、ここから株式市場がどっちの方向に進むかが筆者の目にはまったく映らないのだ。