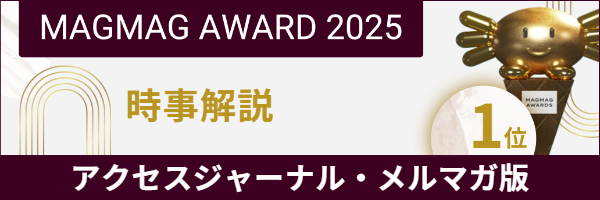*以前の記事はこちらをご覧下さい(ココをクリック)。
新藤厚 1951生まれ(73歳)
1971年 週刊誌記者
79年~84年 テレビレポーター (テレビ朝日・TBS)
84年~99年 「フライデー」記者
99年~2008年 信州で民宿経営
2013年より生活保護開始(24年後半より脱出)
 日当たりのいい山の斜面に金色に光る福寿草を見つけた。
日当たりのいい山の斜面に金色に光る福寿草を見つけた。
田んぼのあぜ道にはオオイヌノフグリの小さな青い花が咲いている。
誰が「犬の金玉」なんて名づけたのか知らないが早春の野山に春の訪れを告げる野草である。
踊子草も蕾を膨らませている。陽光のなかで黄緑色の顔を出しているのはフキノトウである。
里山の登山道をザクザクと霜柱を踏みながら歩いているとスコップで掘り返したように荒れた場所がいくつもある。春先、イノシシが地中のミミズを喰い荒らした食跡である。
田舎は自然の風物が季節を知らせる。
若い頃になじんだ狭斜の巷の酒と女もおもしろかったが、ながく生きて隠居老人になってみると自然を肌身に感じる暮らしぐらい嬉しいことはない。
最強寒波のあとに最長寒波というのがやってきた。また雪が降って山が白一色となった。
雪が降ると里山を歩くのがとても愉快だ。あの登山靴のキュキュという踏み音がなんともいえない。 息を切らして山頂に近づくと新鮮な雪をとって口中にほおばり渇きを癒す。
息を切らして山頂に近づくと新鮮な雪をとって口中にほおばり渇きを癒す。
透析患者は水分制限(一日700ml)がうるさいから清冽な水をごくごく飲むのが見果てぬ夢である。
雪は口いっぱい詰めこんでもほとんど空気だから水分はたかが知れている。
動脈硬化で卒中寸前の血圧も降圧剤を大量に処方されて少し下がった。
といっても170~180だからまだまだ高い。
それを押して医者に禁じられている激しい運動をしている。まあ命がけの山遊びである。
なあに明日死ぬと思えばたいていのことは怖くない。
貧困老人は相変わらず毎日をたのしく遊んで暮らしている。
透析の日を除いて週に四日はそこいらじゅう遊びまくっている。
本読み、お絵描き、山歩きが還暦を過ぎてからの趣味だった。古稀を過ぎ、後期高齢者になってそこに散歩と温泉が加わって老人の生活は飽満である。
知らない町を歩くのは愉しい。何度も書くが亡命者のごとき孤独感を味わえる。放浪漂泊によく似たセンチメントにひたれば仕合せである。
早春の一日、バックパックに温泉セットをつめ老妻とふたりぶらりとプアハウスを出る。
いちばん近い電車の駅は長野と松本をつなぐJR篠ノ井線の稲荷山駅である。林檎畑のなかをゆっくり歩いて30分ほどかかる。 隣の姨捨駅までの切符を買う。身障者割引きで半額だから運賃は100円。
隣の姨捨駅までの切符を買う。身障者割引きで半額だから運賃は100円。
1時間に1本の鈍行(各駅停車)は急傾斜の山の斜面を走る。勾配はキツい。高度が上がってくると千曲川を真ん中に善光寺平の眺望が車窓に展がってくる。
駅を通り越していったん停車すると後進してプラットフォームに入る。姨捨駅は数少なくなったスイッチバックの残る駅である。
「日本の駅人気ランキング」なるものがあるらしい。1位が東京駅で京都、金沢、大阪とつづく。6位が名古屋駅。すべて大都市の歴史ある大ステーションである。
この第5位に山間過疎地の無人駅がいきなりランクインするから驚きだ。
姨捨駅である。
小生は鉄ちゃんにはとんと興味がないが、ホントかね、と信じがたい。
内田百閒、宮脇俊三、関川夏生、原武史なんかの鉄道ものも好きで読んできたが、愛好したのは鉄道ではなく旅情や感傷であった。
休日の電車はシートが埋まるほどの乗客だった。たしかに鉄ちゃんらしき客もいてスマホをかざしたりしている。
だが駅で降りたのはわが老夫婦だけだった。電車が出発して駅を出るともう誰一人いない。寂寞たる田舎駅がそこにあるだけである。
閑散期の三流観光地はツーリズムと無縁である。だから老人の散策にはうってつけだ。
 姨捨駅の下の斜面にひろがる「姨捨棚田」はもう3回ほど歩いている。
姨捨駅の下の斜面にひろがる「姨捨棚田」はもう3回ほど歩いている。
1500枚ともいう小さな不定形の棚田の風景は昔懐かしい郷愁を誘う景観である。
藤原定家の和歌に芭蕉の「更科紀行」、それに歌川広重の「信濃更科田毎月鏡台山」で「姨捨の月と棚田」は古くから都人の人口に膾炙したらしい。
広重の浮世絵は月夜の田一枚一枚に月が映るという現実にはありえないシュールな絵柄である。
この棚田は農耕地では日本で最初に文化財指定を受けたジャパン・ヘリテージである。
田を区切る土を盛った「土坡(どは)」という畦道のアンフォルメル模様が素晴らしい。
いまは田のオーナー制度が人気で都会の観光客が田植えや刈入れにやってくる。
棚田の間の小径をくねくねとゆっくり下っていく。