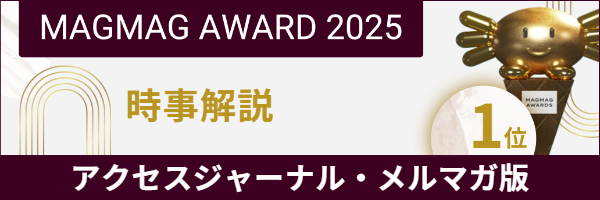*以前の記事はこちらをご覧下さい(ココをクリック)。
新藤厚 1951生まれ(73歳)
1971年 週刊誌記者
79年~84年 テレビレポーター (テレビ朝日・TBS)
84年~99年 「フライデー」記者
99年~2008年 信州で民宿経営
2013年より生活保護開始(24年後半より脱出)
スプリング・エフェメラルという。
春の儚いもの。春の妖精などともいう。
春先、葉のでる前の広葉樹林。その日当たりのいい林床にちいさな花を咲かせる春植物をいう。
フクジュソウ、カタクリ、ニリンソウ、アズマイチゲなどで、花が終わるといつしか姿を消し、地中の根茎や球根で次の春を待つ。 そのなかでも老人がいちばん好きな花が、絶滅危惧種のセツブンソウである。
そのなかでも老人がいちばん好きな花が、絶滅危惧種のセツブンソウである。
その名のとおり温帯の西日本では節分の頃に咲くが、植生北限地の信州では彼岸の頃に花をつける。
近くの里山の斜面にその群生地がある。しっとりとした落葉の斜面一面に白いちいさな花が咲いている。周りの木道を歩いてめでる。気がむくと水絵具でスケッチしたりする。
白く透きとおった花弁に見えるガクのなかに青い雄蕊、紫の雌蕊、黄色の花弁がまとまる。その自然の配色は絶妙である。
見ていると老人のこころも清新な息吹に満たされ、清々しい。
かつては花よりも、紅灯の巷の酒や女だった。あの狂乱の新宿ゴールデン街アル中時代とは隔世の感がする。気がつけば遠くまで来たのだ。
それが年をとるということである。老いるということである。
だから老いることは、意外におもしろいものなのである。
ちなみに花言葉は「人間嫌い」。
ますます老人好みの花ではないか。
 週に三日、人工透析で通っている松代は長芋の産地である。
週に三日、人工透析で通っている松代は長芋の産地である。
この時期、千曲川の河川敷など砂地の畑で、春の長芋の収穫が最盛期である。
畑で多くの小型ユンボ(油圧ショベル)が動いている。重機を動かしているのはカアちゃんやバアちゃんである。1メートルほどの深さの穴を縦に長く穿っていく。
穴のなかで50~60センチほどに育った長芋を、折れないように丁寧に掘り出していくのが男衆の仕事である。
一時代前までは柄の長いスコップで土を掘っていた。見るからに過酷な肉体労働だった。
労働は楽になったかわりに、機械のローンを抱えるのが現代の零細農業である。
老人はスーパーでちいさな長芋を買ってきて、とろろ飯を食す。これも季節の味である。
長芋は春秋の2回収穫する。だからとろろ飯は年に2回食う。旬だとか季節感は日常にメリハリをあたえるので大事にしている。
かつての日本人にはあたりまえの暮らしだったが、その季節感が年々薄らいでいく。
すでに都会は「季節のない街」になった。これを進歩というのか、堕落というのか。
 信州のガソリン代は高い。最近は全国ワースト1位から3位ぐらいの悲惨さである。
信州のガソリン代は高い。最近は全国ワースト1位から3位ぐらいの悲惨さである。
隣接する他県と比べると10円近く高い。
信州に来た頃は「山岳県だから」というエクスキューズを素直に首肯していたが、少し考えればすぐ分かることである。
そんな山の上にスタンドなどないし、県境をまたいだ途端に急に高くなる理由が解せない。
実はガソリンスタンド業界のカルテルは、誰もがうすうす知っていたことである。
今回、公益通報が続発してはじめて証券取引委員会が動いたが、これまで何十年も放置されてきたのはやはり「鄙の論理」だった。