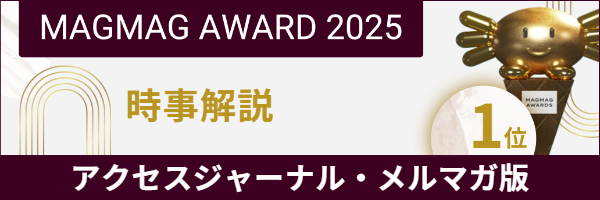*以前の記事はこちらをご覧下さい(ココをクリック)。
新藤厚 1951年生まれ(73歳)
1971年 週刊誌記者
79年~84年 テレビレポーター (テレビ朝日・TBS)
84年~99年 「フライデー」記者
99年~2008年 信州で民宿経営
2013年より生活保護開始(24年後半より脱出)
むかしから半夏生という雑節が好きだった。
一年の折り返しである夏至を過ぎ日は短くなっていくが、まだ梅雨のさなかで青空はまれである。
半夏生までには田植えを終えるというのが、古くからの農事暦だった。
だから半夏生には、雨のなかでひそやかな風情の豊作祈願の祭りが多かった。
盂蘭盆にかさなる夏祭りとはまたひと味違った、落ちついた情緒が好ましかった。
そんな日本の風土に根づいたセンシティブな季節感など、どこかへ行ってしまったようだ。
二千年培われてきた風土が、このたった40年の気候変動で失われている。
かつては豊かな四季のある温帯の秋津島だったわが山河は、二季だけの亜熱帯列島に変貌したのだ。
田舎もまた、ただクソ暑いだけの21世紀ニッポンの夏である。
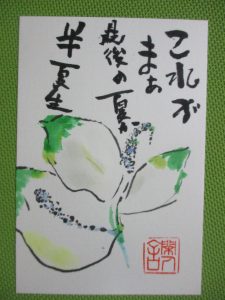 公民館の老人絵手紙教室で、ドクダミに似たハンゲショウの花を描いた。
公民館の老人絵手紙教室で、ドクダミに似たハンゲショウの花を描いた。
文字を添える。「心棒も蝋燭のごと半夏生」。心棒は辛抱のジジイギャグ。
一茶をパクって「これがまあ最後の夏か半夏生」。
言葉も根暗でネガティブだと、卒寿のセンセイに注意された。
年寄りは寒さに弱いと思っていたら、暑熱にもこんなに弱いとは知らなかった。
なんとも不思議なことに老人は暑さをあまり感じないのである。
だから知らぬ間に体温上昇や脱水で生理機能が変調し、ぐったりとして生気を失っている。
気がつけば、ただ加齢臭のする肉袋と化している。
軽度熱中症シンドロームが常態化している。
ちょっと油断するとこのまま死んでしまいそうである。
死ぬまえに好物のいも天が食いたくなって家人に大量に作ってもらった。
これだけ食えばもう死んでもいいや、と心底思った。
人間も動物だから最後は食い物である。
そういえば最後に孫の顔でも見ておくかと、ラインのビデオ通話でふたりの孫と話した。
それでもうこの世にやり残したことなど何もないのである。あした死んでもいいのである。
この哀しいほどの存在の軽さが、死にぞこないの老人である。